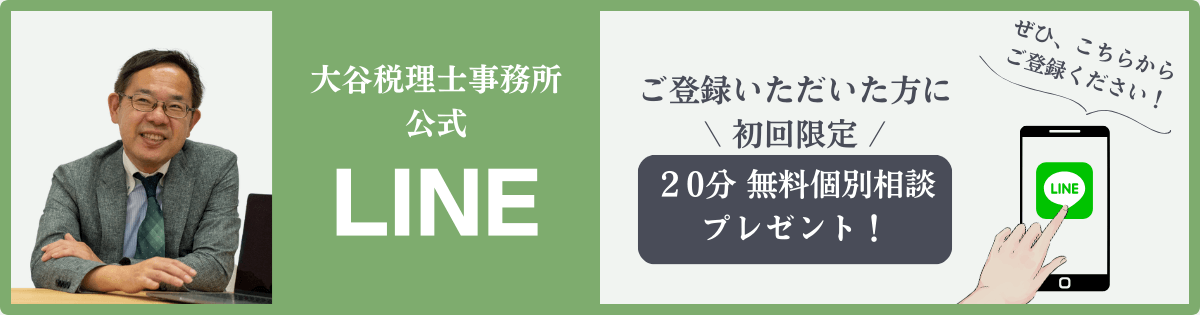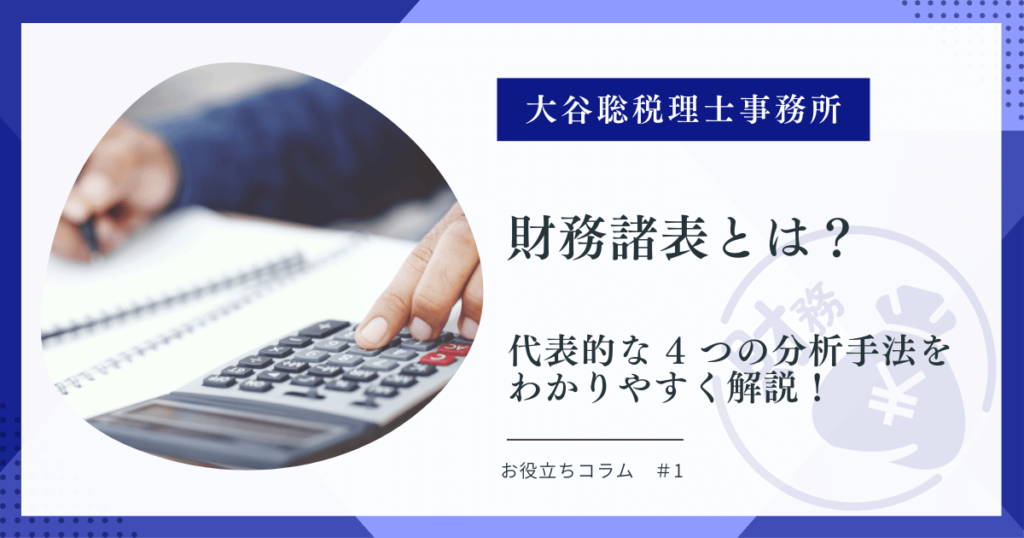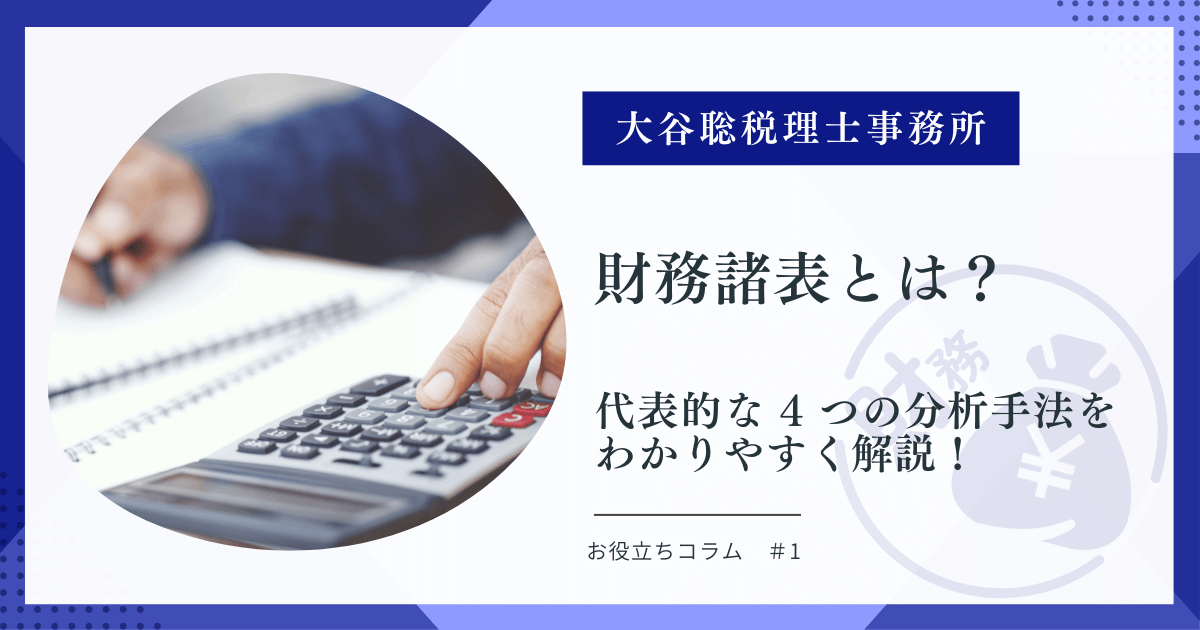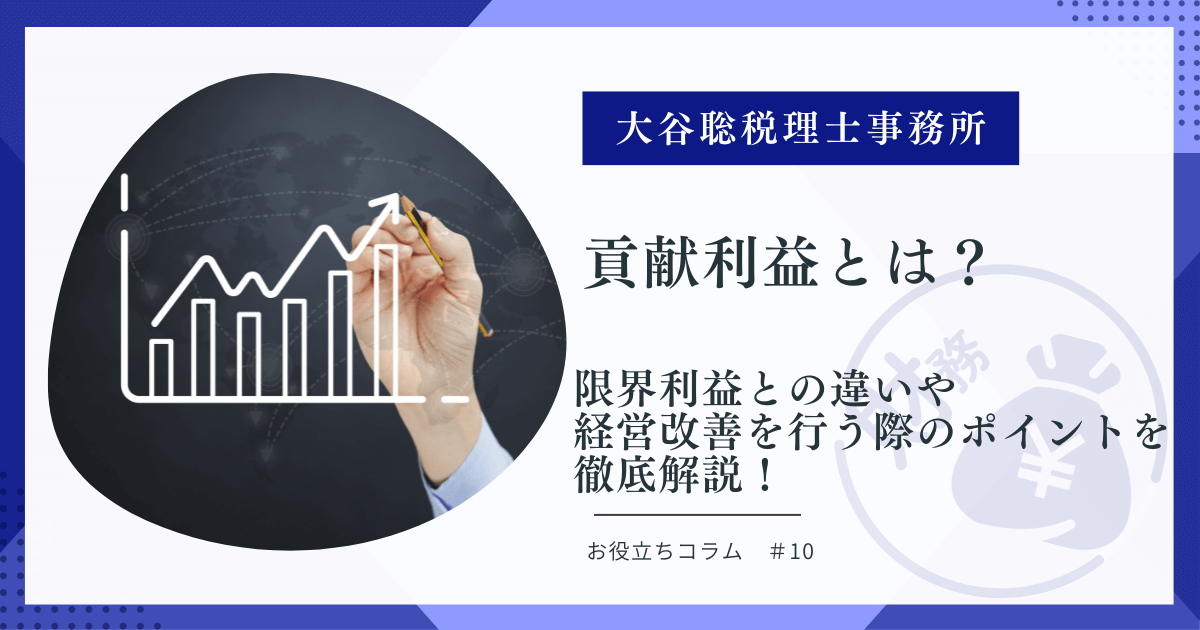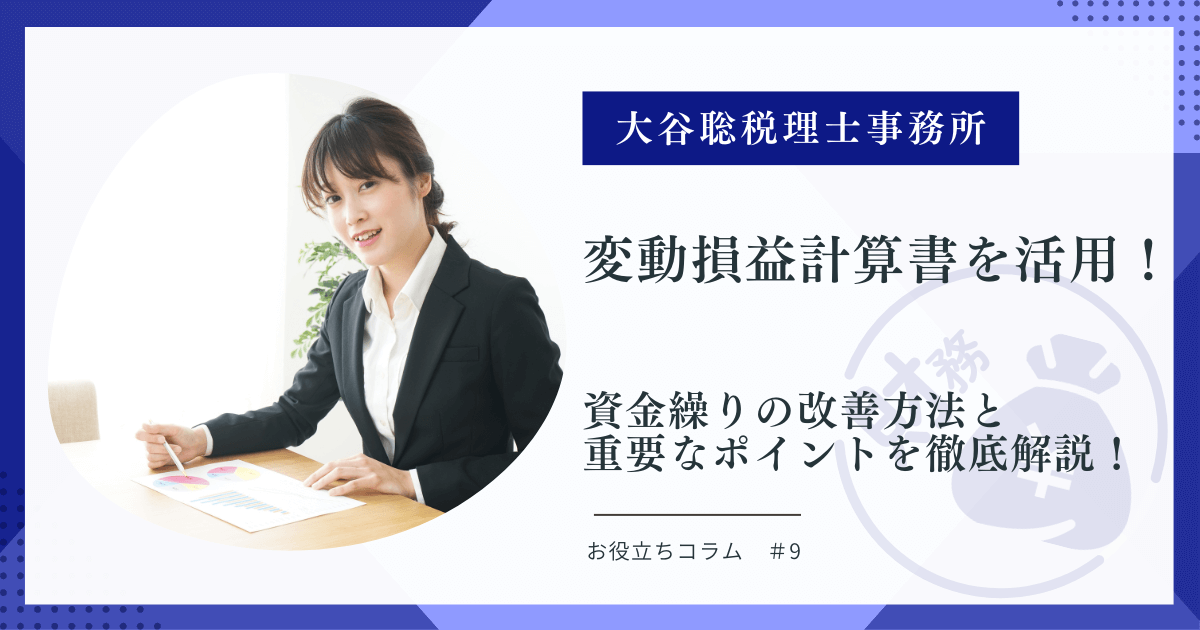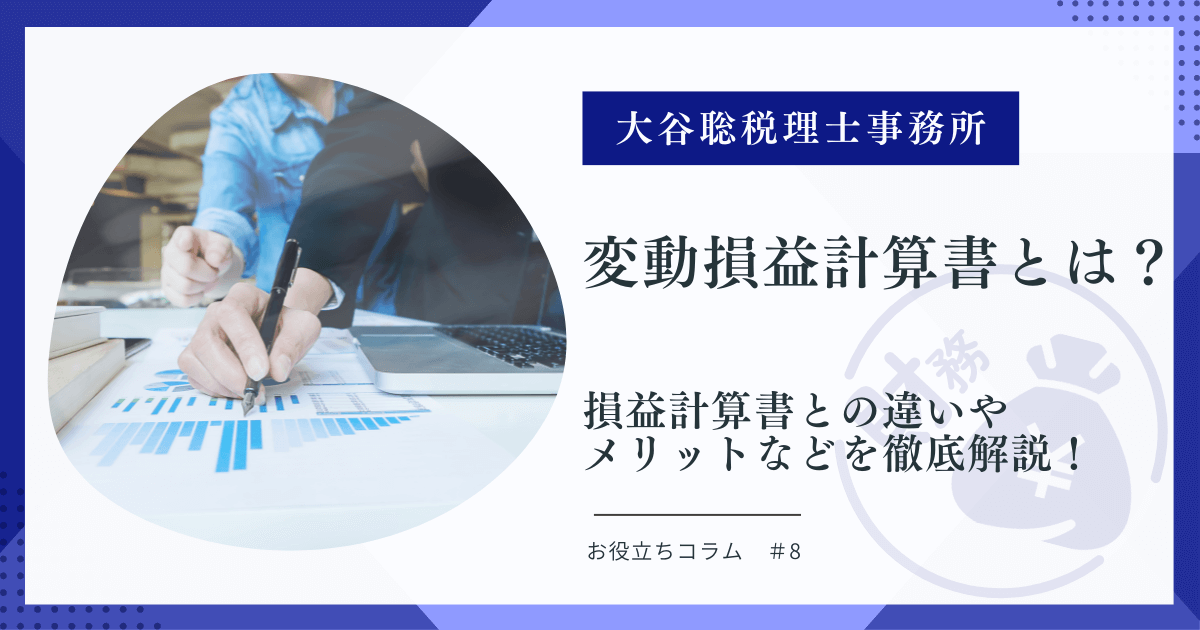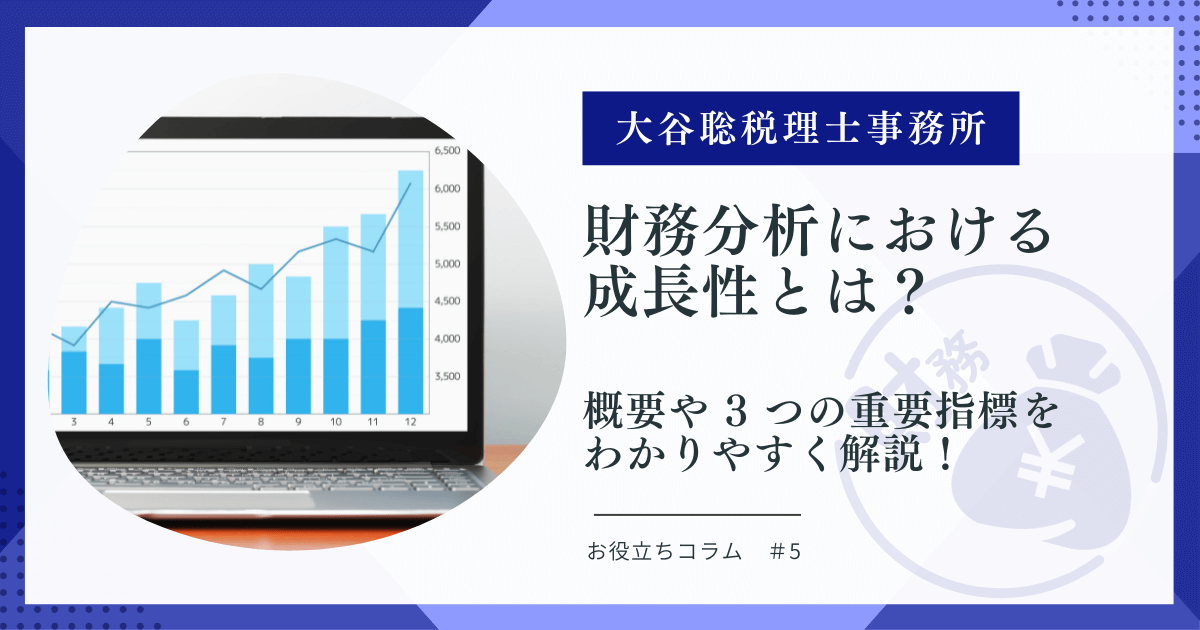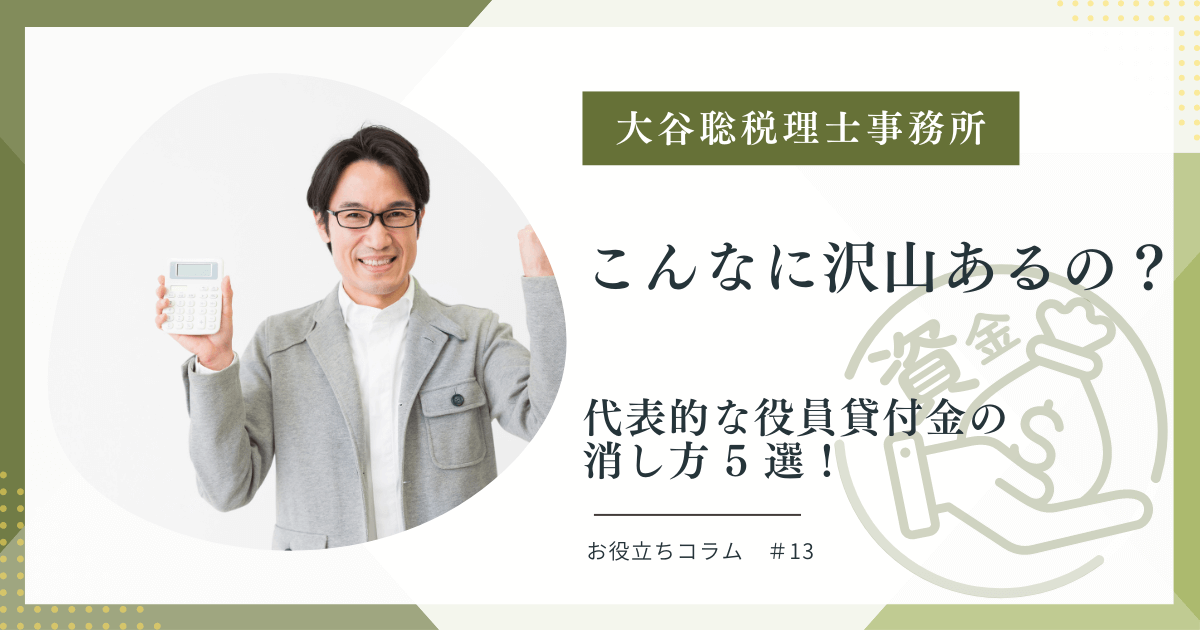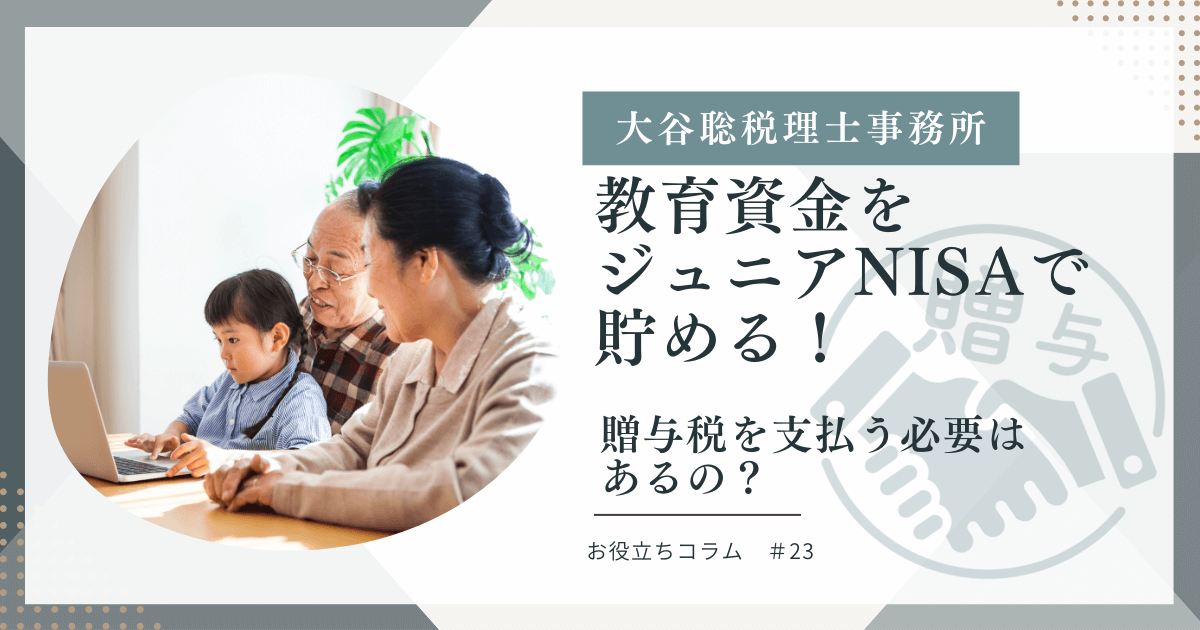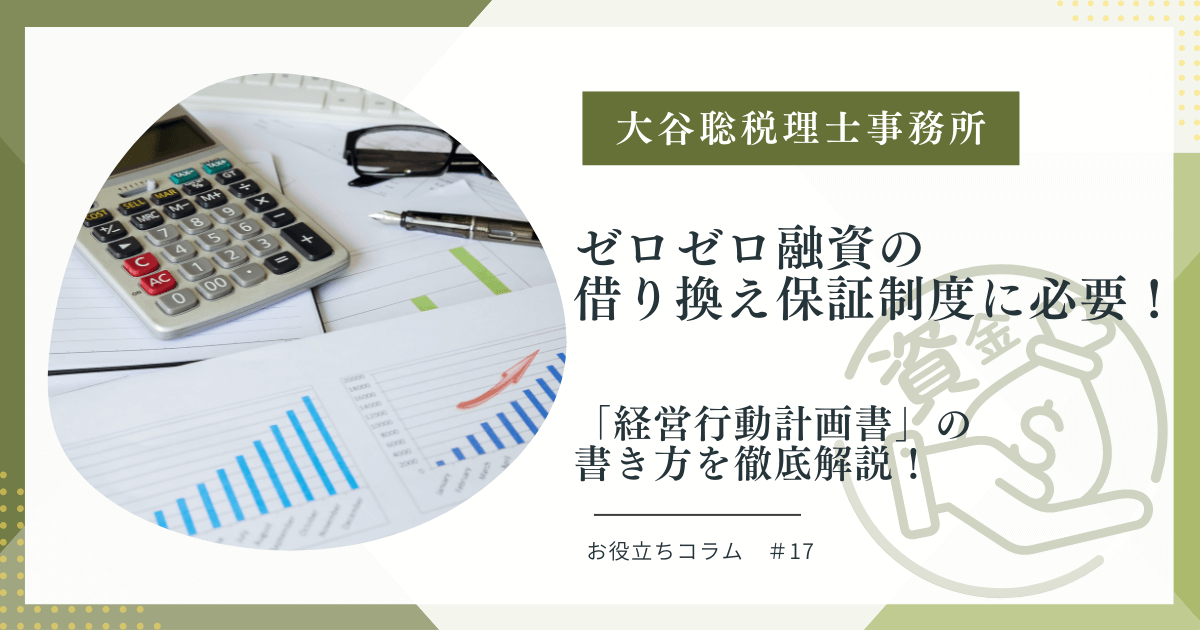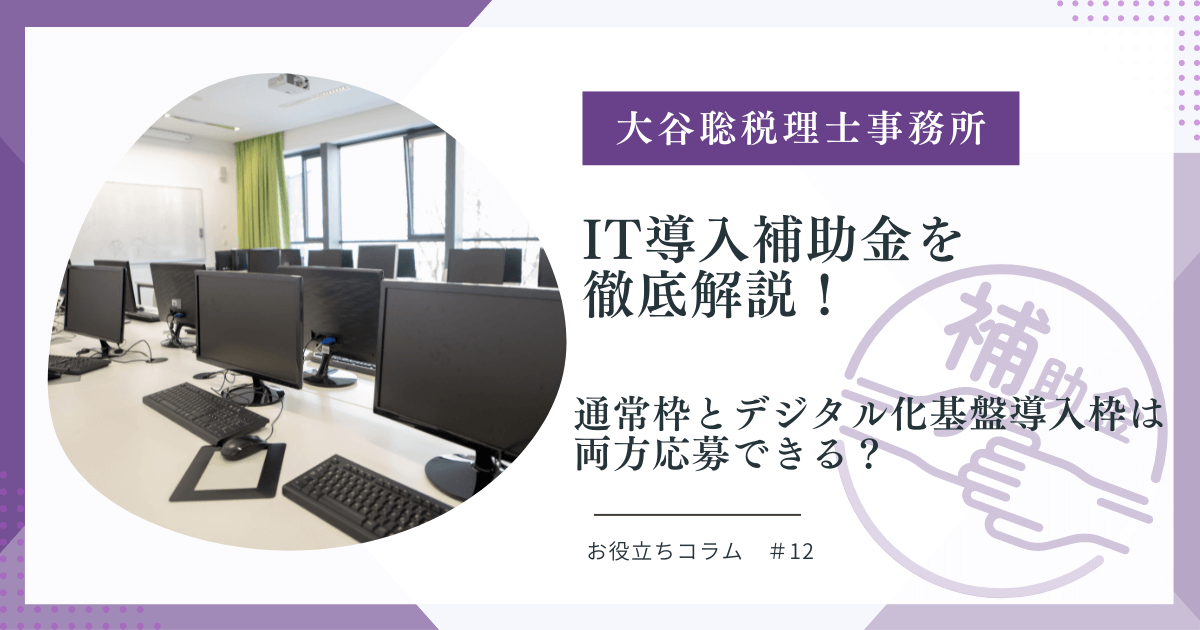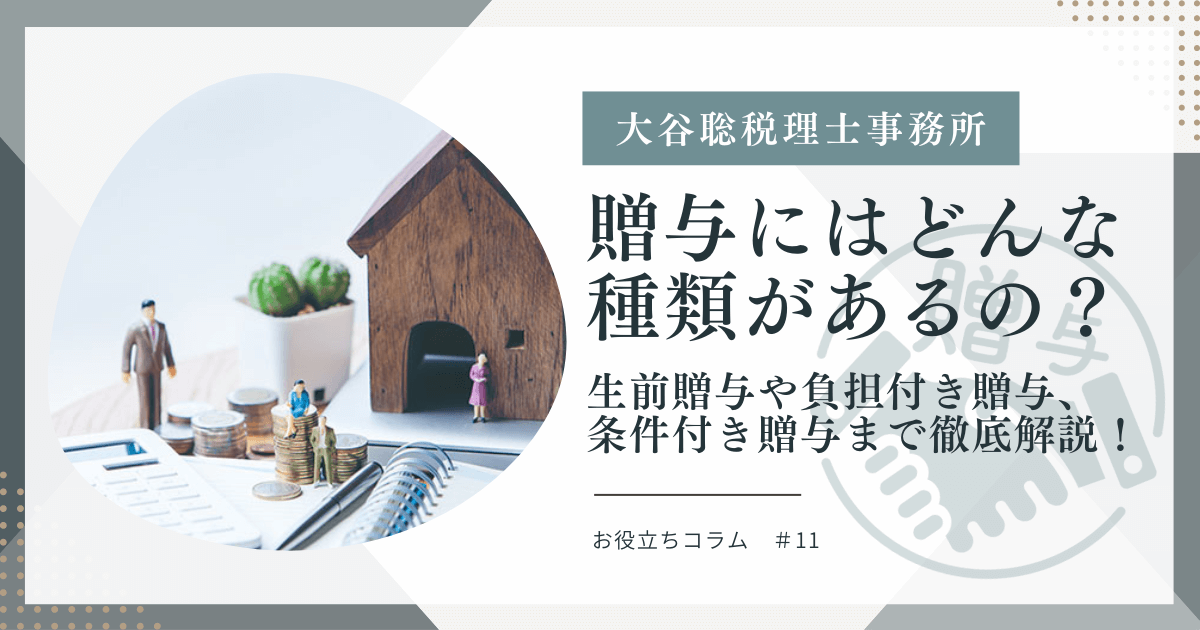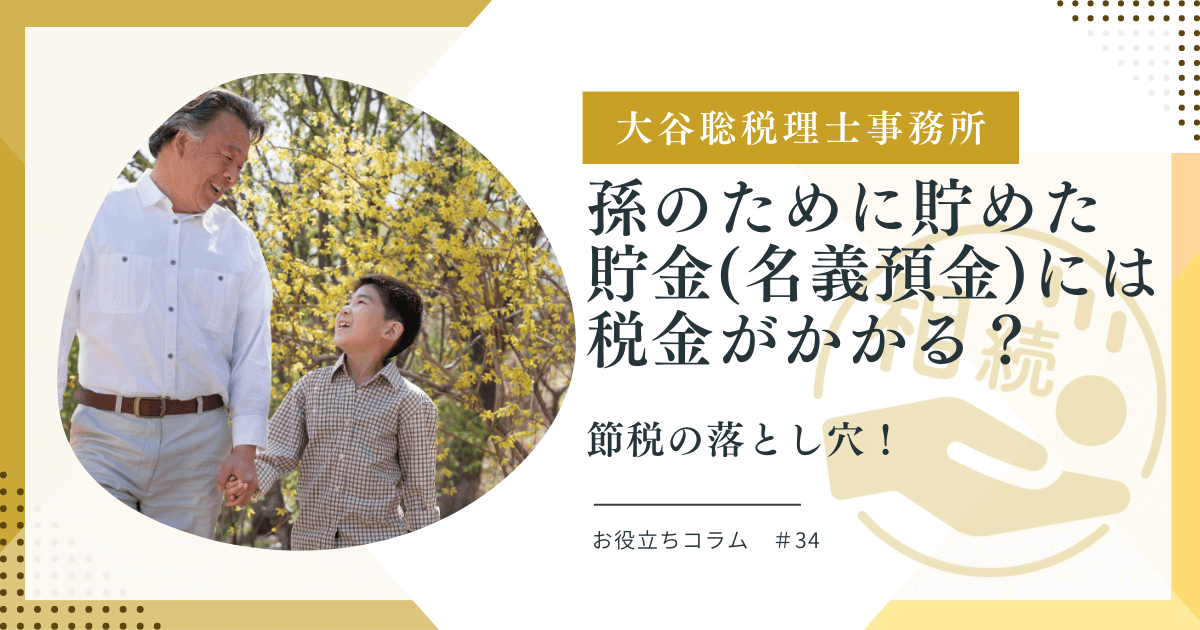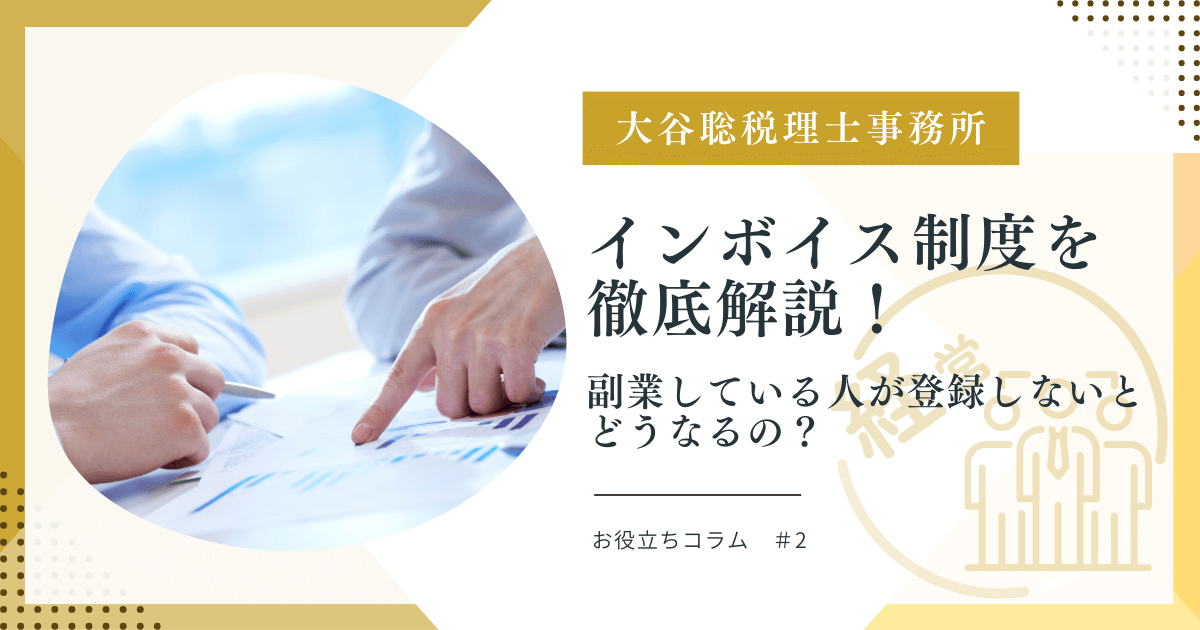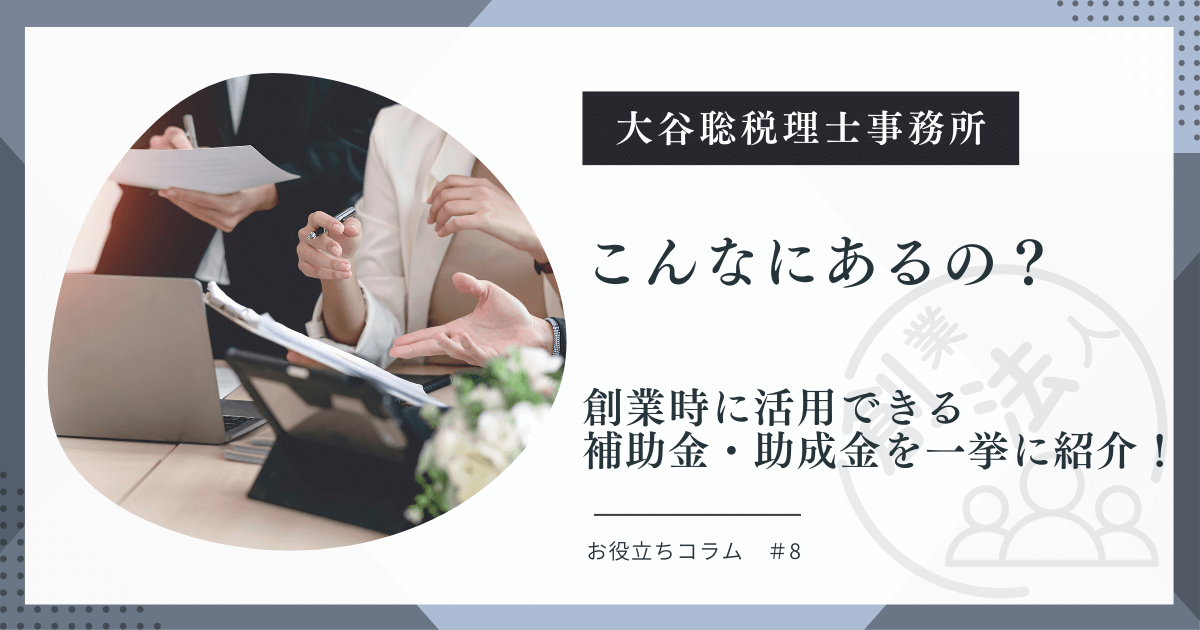Column
お役立ち情報
中小企業経営者に役立つ情報を
お届けします
財務分析における安全性とは?概要や 7 つの重要指標をわかりやすく解説!
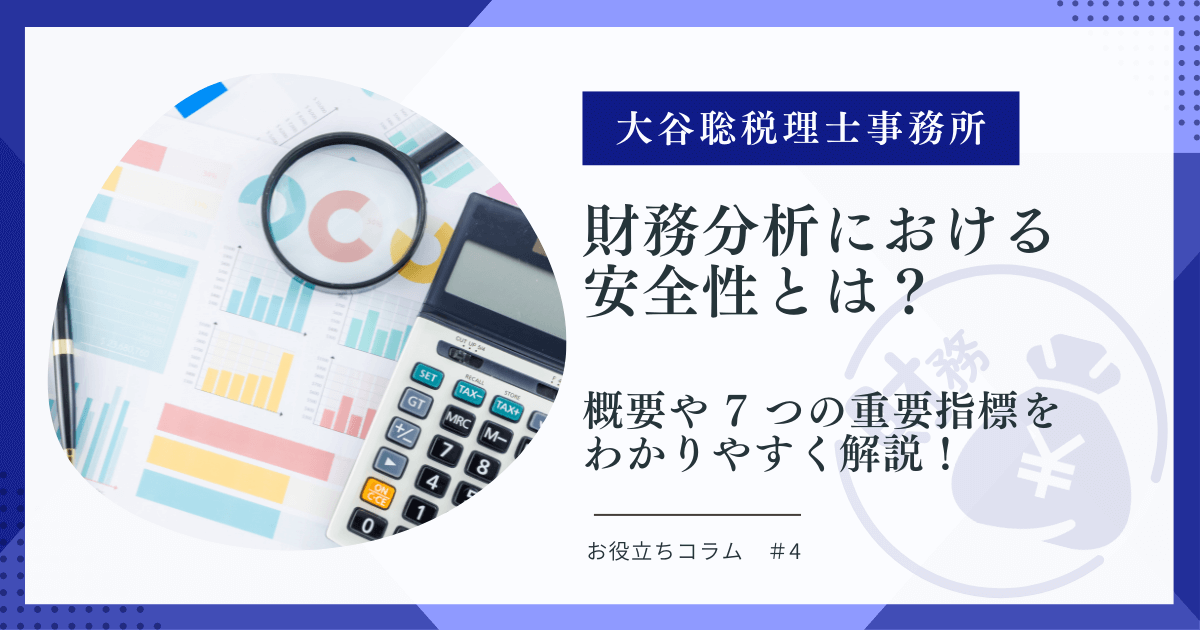
会社の財政状況や経営状況を把握するためには、財務諸表を活用した財務分析が有効な手段になります。しかし、財務分析には様々な分類があり、目的に応じて適切なものを選ぶことが重要なポイントになります。
本記事では、財務分析における分類の一つである「安全性」について、概要や 7 つの重要指標を一挙にご紹介します。財務分析について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。
財務分析とは?
まずは、財務分析の基礎知識についてご説明します。
財務分析とは、財務諸表を分析して様々な指標を算出することを意味します。財務分析を行うことで、会社の現状や課題を見える化でき、今後の戦略策定や意思決定などに繋げることができます。
なお、財務諸表とは、会社の財務に関する様々な書類を総称した言葉であり、次の 3 つが財務諸表の代表例として挙げられます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
ただし、財務諸表という言葉は広義なものであり、状況に応じて「どの書類を指す言葉なのか」が変わります。そのため、上記の 3 つだけが財務諸表というわけではないので、この点には注意してください。
また、貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書の 3 つは「財務三表」とも呼ばれており、財務諸表の中でも特に重要なものとして位置付けられています。
財務分析によって財務諸表の中身を読み解くことで、その会社がどのような財務状況・経営状況にあるのかを読み取ることができます。金融機関から融資を受ける際にも、これらの内容をもとに審査が行われるため、財務分析は会社にとって重要な取り組みの一つであると言えるでしょう。
財務諸表について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
財務分析における「安全性」とは?
財務分析には次の 4 つの分類が存在し、分類ごとに指標や読み取れる内容が異なります。
- 収益性
- 安全性
- 生産性
- 成長性
この中で、今回は「安全性」について詳しくご説明します。
安全性とは、支払能力や倒産リスクなど、その会社の事業の継続性を確認するための指標です。安全性の指標が高いほど、会社が倒産する可能性が低く、安全な経営を実現していることを示します。
そのため、安全性は金融機関や投資家が意思決定を行う際の有効な判断材料になります。金融機関・投資家の目線では、安全性の高い会社に対しては積極的に融資・投資を行いますが、逆に安全性が低い会社は倒産リスクが大きいと判断するため、融資・投資などを控えることが一般的です。
安全性の重要指標
財務分析では、分析作業を行う上で重要となる様々な指標が存在します。そして、実際に財務分析を行う際は、これらの指標をもとに分析作業を進めます。
安全性の主な重要指標としては、
- 流動比率
- 当座比率
- 自己資本比率
- 固定比率
- 固定長期適合率
- 現預金月商比率
- 有利子負債月商比率
などが挙げられます。それでは、各指標について詳しく見ていきましょう。
流動比率
流動比率とは、流動資産に対する流動負債の比率を示す指標です。流動比率の値が高いほど、短期的な支払能力があることを意味しており、流動比率の値が低い場合は資金不足に陥るリスクが高いと言えます。
なお、流動資産とは「 1 年以内に現金化が見込まれる資産」のことであり、売掛金や受取手形などが該当します。そして、流動負債は「 1 年以内に支払期限が訪れる負債」のことであり、買掛金や支払手形などが該当します。
以下、流動比率の算出式です。
流動比率(%)=流動資産 ÷ 流動負債 × 100
当座比率
当座比率とは、流動負債に対する当座資産の比率を示す指標です。なお、当座資産は流動資産から棚卸資産を除くことで算出でき、現金預金や売掛金などが当座資産の具体例として挙げられます。
流動比率と同様に、当座比率も会社の短期的な支払能力を把握するための指標として用いられます。当座比率が高いほど、短期的な支払能力が高いと判断されるため、その会社は倒産リスクが低いと言えます。
以下、当座比率の算出式です。
当座比率(%)=当座資産 ÷ 流動負債 × 100
自己資本比率
自己資本比率とは、総資本に対して自己資本が占める割合を示す指標です。なお、総資本は「自己資本(純資産)」と「他人資本(借入金など)」から構成されています。
自己資本比率の値が高いほど、その会社は安定した経営を行っていることを意味します。一般的には、自己資本比率は 20% から 30% 程度が理想的とされているため、この値を一つの目安にすると良いでしょう。
以下、自己資本比率の算出式です。
自己資本比率(%)= 自己資本 ÷ 総資本 × 100
固定比率
固定比率とは、自己資本に対して固定資産が占める割合を示す指標です。なお、固定資産は長期的に事業で活用される資産のことであり、土地や建物などが該当します。
固定資産に対して投下した資本を回収するためには一定の期間を要するため、固定資産が少ないほど会社の経営が安定していると判断されます。一般的には、固定資産比率が 100% を下回っていれば、長期的な経営状態は安定水準にあると言われているため、この値を一つの目安にすると良いでしょう。
以下、固定比率の算出式です。
固定比率(%)= 固定資産 ÷ 自己資本 × 100
固定長期適合率
固定長期適合率とは、固定負債と自己資本の合計額に対して固定資産が占める割合を示す指標です。なお、固定負債とは、返済期間が 1 年を超えるような負債のことであり、長期借入金などが該当します。
固定長期適合率の値が低いほど、固定資産への投資が健全に行われていることを意味します。一般的には、固定長期適合率が 100% を下回っていれば、健全に固定資産への投資を行っていると判断されるため、この値を一つの目安にすると良いでしょう。
現預金月商比率
現預金月商比率とは、月商の何ヶ月分の現金を保有しているのかを示す指標です。事業を安定的に継続するためには、手元にキャッシュ(現金)を保有しておくことも重要なポイントになります。
現預金月商比率を確認することで、その会社の資金繰りの状況を把握できるため、企業の安全性を測る指標として役立ちます。なお、中小企業の場合、現預金月商比率の目安は 150% 程度と言われています。
以下、現預金月商比率の算出式です。
現預金月商比率(%)=(現金+預金)÷ 月商(年間売上高 ÷ 12 ヶ月)× 100
有利子負債月商比率
有利子負債月商比率とは、月商に対して有利子負債が何ヶ月分あるのかを示す指標です。なお、有利子負債とは、金利(利息)を付けて返済しなければならない負債のことであり、金融機関からの借入金などが該当します。
有利子負債月商比率の値が高いほど、有利子負債を返済できなくなるリスクは大きくなり、安定的に経営を行うことが難しくなります。一般的な中小企業の場合、月商の 3 倍以内であれば問題なく返済可能であり、 6 倍を超えると返済が困難になると言われています。
以下、有利子負債月商比率の算出式です。
有利子負債月商比率(%)=(短期借入金+長期借入金+社債)÷ 月商(年間売上高 ÷ 12)× 100
まとめ
本記事では、財務分析における分類の一つである「安全性」について、概要や 7 つの重要指標を一挙にご紹介しました。
財務分析には様々な分類があり、安全性もその中の一つです。企業の安全性を確認することで、その会社の支払能力や倒産リスクなどを把握し、事業の継続性を測ることができます。
ただし、安全性には数多くの重要指標が存在するため、それぞれの内容や算出方法などを正しく理解し、最低限の知識を有した状態で財務分析を行うことが大切です。
万が一、間違った手順で財務分析を行った場合、正しい結果を得ることができずに安全性を誤認してしまうリスクがあるため、不安な方は専門家へ相談することをオススメします。
そして、財務関連でお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。
無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。
この記事を書いた人
関連記事
よく読まれている記事